Making sense of CRF by data
CRFラボ
No one can fully understand how your body works, except you.
こぐま、桜鯛、ダイエットの効果
5月のはなし
1
毎年5月に入ると、今年はこぐまたちに出会うかな、と思い始める。集落の近くではなく、マウンテンバイクで走っている途中、山のなかの林道での話なので、出会ってみるとその可愛さに、ついついお母さんの熊の存在を忘れがちになる。きっと、冬眠から目覚めてまもないため、お腹が空いているし、食べ盛りの子供達もいるし、大忙しに違いない。
冬眠。同じ哺乳類として、なんと便利なことだろうと、子供の時思ったことがある。ひと冬を寝て過ごせるなんて、一体どれだけの食料を蓄えているのだろう。そういえば、人間でも、ものすごく太ってしまった人が、医師の管理のもと、一年間何も食べずに生活して、無事ダイエットできた話を見かけたことがある。米の袋やら、味噌やら水、で考えると、非常食3ヶ月分みたいな途方もない量になってしまう。脂肪なら蓄えられるなんて、すごい。
1gあたり、脂肪で9kcal、炭水化物なら4kcalのエネルギー[5]を、私たちの体は生成できるという。どうして脂肪の方が多くのエネルギーを生成できるかというと、水分をほとんど含まないからだそうだ。その上、脂肪なら10kg以上たっぷり運べる。そんなに運びたくはありませんけどね。炭水化物はと言うと、体内に貯蔵できるのはわずか数百gにすぎない。運動をしている時で言えば、炭水化物なら1時間、脂肪なら数日分の計算だ。
待てよ、ところで、炭水化物と脂肪、私たちの体はどうやってエネルギー源を選んでいるのだろう?冬眠中に炭水化物がエネルギー源として選択されたら、冬眠に入ったその日のうちに飛び出して餌を探しに行かなければならない。炭水化物をまずは使って、足りなくなったら脂肪を使うのだろうか。
冬眠。同じ哺乳類として、なんと便利なことだろうと、子供の時思ったことがある。ひと冬を寝て過ごせるなんて、一体どれだけの食料を蓄えているのだろう。そういえば、人間でも、ものすごく太ってしまった人が、医師の管理のもと、一年間何も食べずに生活して、無事ダイエットできた話を見かけたことがある。米の袋やら、味噌やら水、で考えると、非常食3ヶ月分みたいな途方もない量になってしまう。脂肪なら蓄えられるなんて、すごい。
1gあたり、脂肪で9kcal、炭水化物なら4kcalのエネルギー[5]を、私たちの体は生成できるという。どうして脂肪の方が多くのエネルギーを生成できるかというと、水分をほとんど含まないからだそうだ。その上、脂肪なら10kg以上たっぷり運べる。そんなに運びたくはありませんけどね。炭水化物はと言うと、体内に貯蔵できるのはわずか数百gにすぎない。運動をしている時で言えば、炭水化物なら1時間、脂肪なら数日分の計算だ。
待てよ、ところで、炭水化物と脂肪、私たちの体はどうやってエネルギー源を選んでいるのだろう?冬眠中に炭水化物がエネルギー源として選択されたら、冬眠に入ったその日のうちに飛び出して餌を探しに行かなければならない。炭水化物をまずは使って、足りなくなったら脂肪を使うのだろうか。
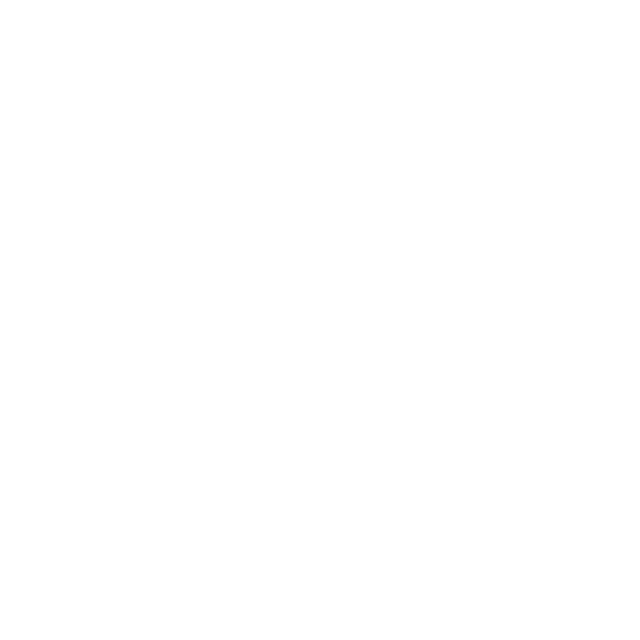
2
鯛をよく見かけるようになるものこの時期。春の鯛は桜鯛と呼ばれるそうだが、鯛と言えば白身のプリプリ、コリコリの刺身だ。ただ我が家で人気があるのは、やはりマグロ。最近子供たちが中トロも食べるようになってしまったが、血の味がするぐらいの赤身が特に人気だ。
実は、この白身と赤身の色の違いは、筋肉の種類からくるもので、人間で言うと、速筋と遅筋に相当するものだ。つまり、白身は、瞬発的に大きな力を出せる筋肉で、赤身は、長時間小さな力を出せる筋肉なのだ。近海で取れる鯛、回遊しているマグロ、それぞれの生態で鍛えられた筋肉を、美味しくいただいていることになる。
人間も、その生態、生活スタイルに応じて筋肉を発達させる。そして、速筋と遅筋では、動かすためのエネルギー源が異なる。速筋を動かすために必要なエネルギー源は、炭水化物から生成される糖だが、遅筋は脂肪を使う。つまり、炭水化物と脂肪、私たちの体がどちらのエネルギー源を使うかは、必要とされる筋肉によるのだ[6]。
実は、この白身と赤身の色の違いは、筋肉の種類からくるもので、人間で言うと、速筋と遅筋に相当するものだ。つまり、白身は、瞬発的に大きな力を出せる筋肉で、赤身は、長時間小さな力を出せる筋肉なのだ。近海で取れる鯛、回遊しているマグロ、それぞれの生態で鍛えられた筋肉を、美味しくいただいていることになる。
人間も、その生態、生活スタイルに応じて筋肉を発達させる。そして、速筋と遅筋では、動かすためのエネルギー源が異なる。速筋を動かすために必要なエネルギー源は、炭水化物から生成される糖だが、遅筋は脂肪を使う。つまり、炭水化物と脂肪、私たちの体がどちらのエネルギー源を使うかは、必要とされる筋肉によるのだ[6]。
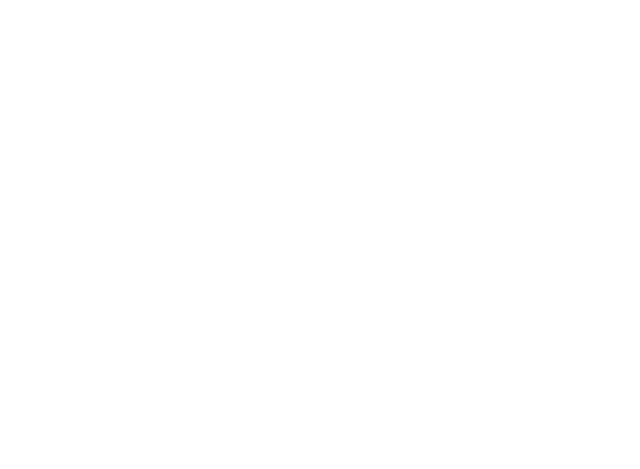
3
スポーツ科学の分野では、運動中の生理学的な作用の研究が驚くほど進んでいる。もちろん、どの速筋、または遅筋、を使うか、選んで意図的に使うことはできないが、どちらをどれぐらい使っているかを、かなり正確に知ることができる。そんなことが何になるのかというと、運動強度を生理学的に定義できるようになり、その結果、より効率的なトレーニングが可能になる。特定の筋肉を効率よくトレーニングできるのは、何もアスリートにだけメリットがあるのではなく、むしろ中年で肥満になってきた私のようなおじさん、おばさんへのメリットが大きい。
CRF(心肺フィットネス)に関する研究[1][2]によると、最も低いグループから次に低いグループへフィットネスが改善すると、全死因死亡率が半分以上低下する。細かく言うと、1 METフィットネスが改善する毎に、全死因死亡率は13%、心血管疾患の罹患率は15%低下する。メタボでお馴染みの指標でもっと細かく言うことだってできて、1 METフィットネスが改善する毎に、ウェストなら-7cm、収縮期血圧なら-5mmHg、男性の中性脂肪なら-1mmol/L、空腹時血糖値も-1mmol/L、そして善玉コレステロールなら0.2mmol/Lの増加につながる。もちろん、統計的な値なので、必ずそうなるわけではもちろんないが、個人的な感想、よりはもっともらしい期待値だ。ちなみに、1 METというのは、酸素の摂取量に基づく運動強度の単位で、安静時の摂取量(3.5 mL/min/kg)に相当する強度のこと。これを使えば、運動強度を客観的に定義することができるため、「全死因死亡率と心血管疾患の罹患率が大幅に低下する最大酸素摂取量(VO2Max)の目安は、40歳で7~9METs、50歳で6~8METs、60歳で5~7METs」などと言うこともできるのだ。
CRF(心肺フィットネス)に関する研究[1][2]によると、最も低いグループから次に低いグループへフィットネスが改善すると、全死因死亡率が半分以上低下する。細かく言うと、1 METフィットネスが改善する毎に、全死因死亡率は13%、心血管疾患の罹患率は15%低下する。メタボでお馴染みの指標でもっと細かく言うことだってできて、1 METフィットネスが改善する毎に、ウェストなら-7cm、収縮期血圧なら-5mmHg、男性の中性脂肪なら-1mmol/L、空腹時血糖値も-1mmol/L、そして善玉コレステロールなら0.2mmol/Lの増加につながる。もちろん、統計的な値なので、必ずそうなるわけではもちろんないが、個人的な感想、よりはもっともらしい期待値だ。ちなみに、1 METというのは、酸素の摂取量に基づく運動強度の単位で、安静時の摂取量(3.5 mL/min/kg)に相当する強度のこと。これを使えば、運動強度を客観的に定義することができるため、「全死因死亡率と心血管疾患の罹患率が大幅に低下する最大酸素摂取量(VO2Max)の目安は、40歳で7~9METs、50歳で6~8METs、60歳で5~7METs」などと言うこともできるのだ。
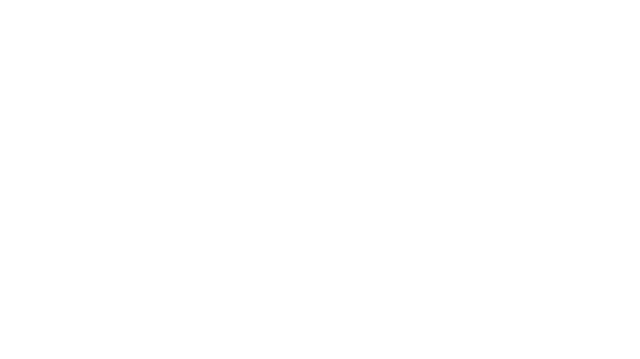
4
運動強度を生理学的に定義するのは、4つの閾値で、強度の高い順から、VO2Max、AnT(Anaerobic Threshold、AT、VT2、LT2とも呼ばれる)、AerT
(Aerobic Threshold、VT1、LT1とも呼ばれる)、そして最近研究が進んでいるFat Maxだ。VO2Maxが、これ以上は無理!、という限界値なのは想像がつくだろうが、AnTとAerTは、それぞれ速筋と遅筋がメインで使われる境目の強度のことなのだ。つまり、安静時から徐々に強度を上げて運動をしていく時、AerTまでは脂肪を燃焼させてほとんど遅筋だけで運動し、AnT以降は、糖を使ってほとんど速筋だけで運動する。AerTとAnTの間は両者が混在し、AerTからAnTに向かって速筋の比率が増えていく。Fat Maxは、脂肪を最も多く燃焼できる閾値のことで、AerTよりもわずかに低いことがわかっている[3]。そして、これら4つの閾値は、人によって大きく異なるのだ。
ここまでの説明でピンと来たかもしれないが、同じ運動をしても人によって効果が異なるのは、この閾値が異なるからだ。ある人にとっては、ちょうどFat Maxに相当して最も効率よく脂肪を燃焼させて痩せる運動が、別な人にっては速筋主体の運動となり、糖が枯渇して甘いものが食べたくなる結果にもなりうるのだ。
ちなみに、Fat Maxの研究が最近進んでいるのは、アスリート、アスリートでない人、疾患を抱えている人、多くの人にとって、赤身の筋肉の重要性が明らかになってきているからだろう。
アスリート、特にエンデュランスアスリートにとっては、AerTが高いほど、脂肪をエネルギー源とする、筋肉の劣化が少ない赤身の筋肉を使うことができるため、AerTを向上させることが競争力の源泉となってきた。このため、AerT未満の低強度の運動を主体にして、AnT超の高強度の運動を混ぜる、Polarized型(AerTからAnTの中強度の運動比率が低い)のトレーニング構成が一般的になっている。これは、疲労の回復と赤身の筋肉のトレーニングに必要な時間を確保しながら、いわゆるメリハリによって効率よく筋肉を成長させる効果があるそうだ。
アスリートでない人、ちょっとメタボ気味の人にとっても赤身の効果は絶大だ。メタボになってくると、赤身の筋肉が縮小し、白身の筋肉の割合が増えてくる。そうすると、脂肪が燃やせず、炭水化物(糖)が欲しい体になり、メタボ化が進む。このメタボサイクルを逆回転させるには、Fat Max付近、AerTよりもちょっと低いぐらいの低強度の運動を始めることだ。もし私が今から始めるなら、インドアトレーナーで、テレビを見ながらとか、綺麗な観光地の景色を見ながら走りたい。それなら、1時間ぐらいはできるだろう。直感に反するが、とにかく汗かくほどやらない程度の強度がFat Max付近になるので、まずはこれを掴んでしまえば、続けるのは難しくないし、何より激しい運動につきもののケガとは無縁だ。
疾患を抱えている人、例えば2型糖尿病の原因の一つは、インスリンに反応しなくなるインスリン抵抗性だが、インスリンに主に反応するのは赤身の筋肉であり、これが縮小して機能が低下することにより2型糖尿病を発症することが分かってきているそうだ[4]。
最後に、これらの因果関係を、現時点で分かっている範囲でGraphical Causal Modelにまとめた。矢印の元を辿っていくことで根本原因に近づいていくのだが、逆に言うと根本原因を解決することで各種の問題が芋蔓式に解決されることになる。Fat MaxやAerTがそうした根本原因の位置にあることが、最近研究が進んでいる理由ではないだろうか。
技術的な詳細はまた別の機会にまとめるが、将来的に実現したいのはこういうことである。
「たとえばAerTがxの人が、メタボ指数MetSynをzに改善したい場合、Training ModelのAとBでは、実現する可能性がどちらがどれだけ高いか」
これは、以下のように評価される。
P(MetSys=z|do(TrainingModel=A), AerT=x) - P(MetSys=z|do(TrainingModel=B), AerT=x)
(Aerobic Threshold、VT1、LT1とも呼ばれる)、そして最近研究が進んでいるFat Maxだ。VO2Maxが、これ以上は無理!、という限界値なのは想像がつくだろうが、AnTとAerTは、それぞれ速筋と遅筋がメインで使われる境目の強度のことなのだ。つまり、安静時から徐々に強度を上げて運動をしていく時、AerTまでは脂肪を燃焼させてほとんど遅筋だけで運動し、AnT以降は、糖を使ってほとんど速筋だけで運動する。AerTとAnTの間は両者が混在し、AerTからAnTに向かって速筋の比率が増えていく。Fat Maxは、脂肪を最も多く燃焼できる閾値のことで、AerTよりもわずかに低いことがわかっている[3]。そして、これら4つの閾値は、人によって大きく異なるのだ。
ここまでの説明でピンと来たかもしれないが、同じ運動をしても人によって効果が異なるのは、この閾値が異なるからだ。ある人にとっては、ちょうどFat Maxに相当して最も効率よく脂肪を燃焼させて痩せる運動が、別な人にっては速筋主体の運動となり、糖が枯渇して甘いものが食べたくなる結果にもなりうるのだ。
ちなみに、Fat Maxの研究が最近進んでいるのは、アスリート、アスリートでない人、疾患を抱えている人、多くの人にとって、赤身の筋肉の重要性が明らかになってきているからだろう。
アスリート、特にエンデュランスアスリートにとっては、AerTが高いほど、脂肪をエネルギー源とする、筋肉の劣化が少ない赤身の筋肉を使うことができるため、AerTを向上させることが競争力の源泉となってきた。このため、AerT未満の低強度の運動を主体にして、AnT超の高強度の運動を混ぜる、Polarized型(AerTからAnTの中強度の運動比率が低い)のトレーニング構成が一般的になっている。これは、疲労の回復と赤身の筋肉のトレーニングに必要な時間を確保しながら、いわゆるメリハリによって効率よく筋肉を成長させる効果があるそうだ。
アスリートでない人、ちょっとメタボ気味の人にとっても赤身の効果は絶大だ。メタボになってくると、赤身の筋肉が縮小し、白身の筋肉の割合が増えてくる。そうすると、脂肪が燃やせず、炭水化物(糖)が欲しい体になり、メタボ化が進む。このメタボサイクルを逆回転させるには、Fat Max付近、AerTよりもちょっと低いぐらいの低強度の運動を始めることだ。もし私が今から始めるなら、インドアトレーナーで、テレビを見ながらとか、綺麗な観光地の景色を見ながら走りたい。それなら、1時間ぐらいはできるだろう。直感に反するが、とにかく汗かくほどやらない程度の強度がFat Max付近になるので、まずはこれを掴んでしまえば、続けるのは難しくないし、何より激しい運動につきもののケガとは無縁だ。
疾患を抱えている人、例えば2型糖尿病の原因の一つは、インスリンに反応しなくなるインスリン抵抗性だが、インスリンに主に反応するのは赤身の筋肉であり、これが縮小して機能が低下することにより2型糖尿病を発症することが分かってきているそうだ[4]。
最後に、これらの因果関係を、現時点で分かっている範囲でGraphical Causal Modelにまとめた。矢印の元を辿っていくことで根本原因に近づいていくのだが、逆に言うと根本原因を解決することで各種の問題が芋蔓式に解決されることになる。Fat MaxやAerTがそうした根本原因の位置にあることが、最近研究が進んでいる理由ではないだろうか。
技術的な詳細はまた別の機会にまとめるが、将来的に実現したいのはこういうことである。
「たとえばAerTがxの人が、メタボ指数MetSynをzに改善したい場合、Training ModelのAとBでは、実現する可能性がどちらがどれだけ高いか」
これは、以下のように評価される。
P(MetSys=z|do(TrainingModel=A), AerT=x) - P(MetSys=z|do(TrainingModel=B), AerT=x)
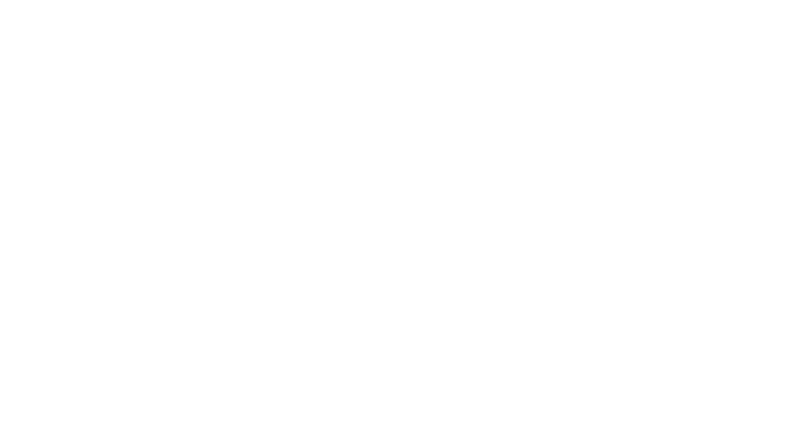
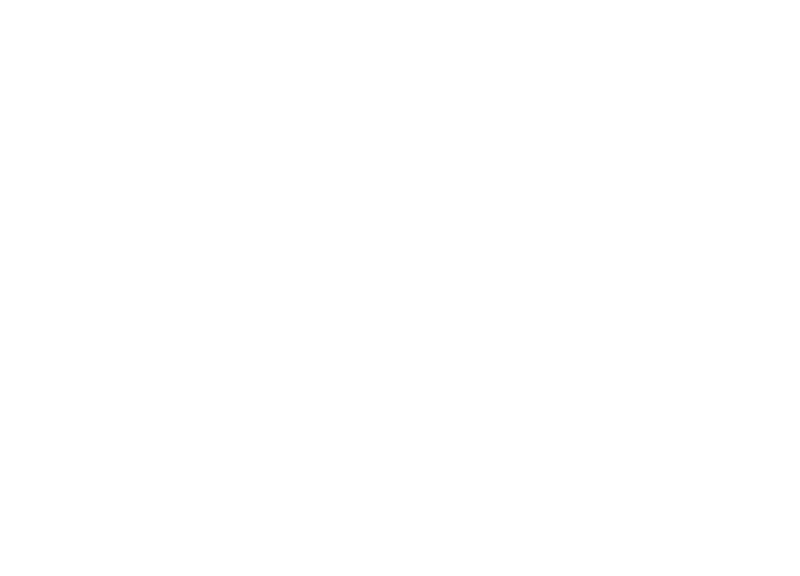
5
健康は、体も心も、大量生産品ではフィットしない。理解してあげて、フィットさせられるのは自分しかいない。まずは、理解するために必要な知識を手に入れる。そうすることで、誰かが何かの目的で言ったものを、分解して、判断できるようになる。そうすれば、自分にフィットするように取り込むことが可能になる。
なぜAerTとAnTは計測可能なのか。計測方法の理屈が分かったら、後は計測するだけ。計測して現在地が見えるようになれば、目的地へ近づいているのか遠くなっているのかが見えるから。次回はこのあたりの謎を解き明かします。
なぜAerTとAnTは計測可能なのか。計測方法の理屈が分かったら、後は計測するだけ。計測して現在地が見えるようになれば、目的地へ近づいているのか遠くなっているのかが見えるから。次回はこのあたりの謎を解き明かします。
R
出典
- Kodama S, Saito K, Tanaka S, Maki M, Yachi Y, Asumi M, Sugawara A, Totsuka K, Shimano H, Ohashi Y, Yamada N, Sone H. Cardiorespiratory fitness as a quantitative predictor of all-cause mortality and cardiovascular events in healthy men and women: a meta-analysis. JAMA. 2009; 301:2024–2035. doi: 10.1001/jama.2009.681.
- Ross, Robert; Blair, Steven N.; Arena, Ross; Church, Timothy S.; Després, Jean-Pierre; Franklin, Barry A.; Haskell, William L.; Kaminsky, Leonard A.; Levine, Benjamin D.; Lavie, Carl J.; Myers, Jonathan; Niebauer, Josef; Sallis, Robert; Sawada, Susumu S.; Sui, Xuemei (2016-12-13). "Importance of Assessing Cardiorespiratory Fitness in Clinical Practice: A Case for Fitness as a Clinical Vital Sign: A Scientific Statement From the American Heart Association". Circulation. 134 (24): e653–e699. doi:10.1161/CIR.0000000000000461
- Ferri Marini C, Tadger P, Chávez-Guevara IA, Tipton E, Meucci M, Nikolovski Z, Amaro-Gahete FJ, Peric R. Factors Determining the Agreement between Aerobic Threshold and Point of Maximal Fat Oxidation: Follow-Up on a Systematic Review and Meta-Analysis on Association. Int J Environ Res Public Health. 2022 Dec 27;20(1):453. doi: 10.3390/ijerph20010453. PMID: 36612784; PMCID: PMC9819531.
- Stuart CA, McCurry MP, Marino A, South MA, Howell ME, Layne AS, Ramsey MW, Stone MH. Slow-twitch fiber proportion in skeletal muscle correlates with insulin responsiveness. J Clin Endocrinol Metab. 2013 May;98(5):2027-36. doi: 10.1210/jc.2012-3876. Epub 2013 Mar 20. PMID: 23515448; PMCID: PMC3644602.
- United Nations Food and Agriculture Organization (2003): "FAO Food and Nutrition Paper 77: Food energy - methods of analysis and conversion factors Archived 2010-05-24 at the Wayback Machine".
- Bourdeau Julien I, Sephton CF, Dutchak PA. Metabolic Networks Influencing Skeletal Muscle Fiber Composition. Front Cell Dev Biol. 2018 Sep 28;6:125. doi: 10.3389/fcell.2018.00125. PMID: 30324104; PMCID: PMC6172607.
佐藤 剛宣
Takenori Sato
Takenori Sato
株式会社TMT代表取締役、健康エンジニア
山梨県北杜市明野町在住、妻と4人の子供の6人暮らし。趣味は自転車。これまでの経験を生かして、2024年からは、運動と遊びに取り組んでいる。Computer ScienceのInformation Retrieval(データを保存し、情報として取得する技術の総称で、データベース、検索エンジン、ビッグデータ基盤と分析からAIまで)関連スタートアップで20年の経験を持つ。
1998年(当時)運輸省航空大学校飛行機操縦課卒業
2005年 db4objects(シリコンバレーの組み込みオブジェクトデータベース開発スタートアップ)日本代表
2018年 EDGEMATRIX株式会社 常務執行役員
2024年 現職
1998年(当時)運輸省航空大学校飛行機操縦課卒業
2005年 db4objects(シリコンバレーの組み込みオブジェクトデータベース開発スタートアップ)日本代表
2018年 EDGEMATRIX株式会社 常務執行役員
2024年 現職
© 2024 All Rights Reserved
takenori.sato@gmail.com
takenori.sato@gmail.com

