Creative Thinkerになろう
子どものためのScratch活用方法
小学校のプログラミングの授業で利用されるScratch。その思想を辿ると、およそ「プログラミング」というイメージからは想像できなかった、広大な創造の地平線が見えてくる。
1
今年度に入ってから、もともとやる気に溢れていた次女の成長が加速し、我が家では次女を「学校大臣」と呼ぶまでになったが、そのやる気と成長を引き出してくれているのが、今年度から始まった小学校の新しい取り組み、「あけのスタイルプロジェクト」通称ASPだ。
ASPとは、「自分のすきなこと、きょうみのあることをいかして、学ぶ場所、学ぶ内容、学びの計画、を自分で決めて進める」時間のことで、教職員も参加する。同じような関心テーマを持つ子どもたちと教職員、そしてそれをサポートしたい保護者が、同じ空間に集まってプロジェクトを進める。
次女のプロジェクトは、Scratchでプラットフォーマーゲーム(スーパーマリオのようなゲームのこと)を作って、そのやり方を発表する、というものだ。
Scratchとは、小学校のプログラミング教育で主に採用されているツールだが、「小学校プログラミング教育に関する研修教材」の中で、2つ紹介されているビジュアル型プログラミング言語の一つに該当する。この資料の中で、「小学校プログラミング教育の概要 1」というものがあり、そこには「なぜ小学校でプログラミング教育を導入するのか」と「小学校プログラミング教育のねらい、育もうとする資質・能力とは」が明記されている。ここでは、特にこのねらいについて、紹介したい。
図1がそれだが、文部科学省が定める小学校のプログラミング教育のねらいは、プログラミングの習得それ自体がねらいではないものの、「プログラミング的思考」に重点が置かれていることが分かる。この「プログラミング的思考」は、以下のように定義されている。
「プログラミング的思考」とは、「自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せ が必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組合せをど のように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力」
私はどうしてもこれが腑に落ちないのだが、ここでは深入りせず、紹介にとどめておく。
ASPとは、「自分のすきなこと、きょうみのあることをいかして、学ぶ場所、学ぶ内容、学びの計画、を自分で決めて進める」時間のことで、教職員も参加する。同じような関心テーマを持つ子どもたちと教職員、そしてそれをサポートしたい保護者が、同じ空間に集まってプロジェクトを進める。
次女のプロジェクトは、Scratchでプラットフォーマーゲーム(スーパーマリオのようなゲームのこと)を作って、そのやり方を発表する、というものだ。
Scratchとは、小学校のプログラミング教育で主に採用されているツールだが、「小学校プログラミング教育に関する研修教材」の中で、2つ紹介されているビジュアル型プログラミング言語の一つに該当する。この資料の中で、「小学校プログラミング教育の概要 1」というものがあり、そこには「なぜ小学校でプログラミング教育を導入するのか」と「小学校プログラミング教育のねらい、育もうとする資質・能力とは」が明記されている。ここでは、特にこのねらいについて、紹介したい。
図1がそれだが、文部科学省が定める小学校のプログラミング教育のねらいは、プログラミングの習得それ自体がねらいではないものの、「プログラミング的思考」に重点が置かれていることが分かる。この「プログラミング的思考」は、以下のように定義されている。
「プログラミング的思考」とは、「自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せ が必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組合せをど のように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力」
私はどうしてもこれが腑に落ちないのだが、ここでは深入りせず、紹介にとどめておく。
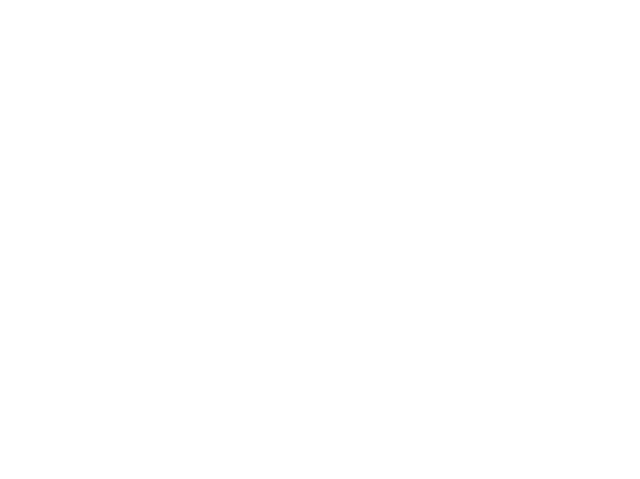
図1 小学校プログラミング教育のねらい
2
Scratchは、GoogleのBlocklyをベースに開発されているが、同じようにBlocklyをベースにしたもので、我が家でお馴染みなのは、Microsoft MakeCode Arcadeだ。Blocklyは、ブロックの組みわせで「文字列」を生成するツールのことで、通常はプログラミングのコードを文字列として生成するのだが、何を生成するか、どのようなブロックを用意するかは、Blocklyの使い方次第で、Microsoft Make Code Arcadeは、子ども達の関心が高いゲームに特化しているのが特徴だ。ブロックで作成しながら、PythonやJavascriptのようなプログラミング言語と双方向で記述できたり、図2のようなマイコンのコンピューターで作ったゲームを動かすことができる。また、Microsoft MakeCodeには、Arcade以外にも派生したツールがあるため、子どもの関心に応じて、対応できる選択肢が豊富だ。
そのため、Scratchの先の方向性、例えば、夏休みの自由研究で大いに活用できそうな「データ分析」、たくさんの子どもたちが夢中になっている「ゲーム」、それからアクセサリーやおもちゃなどのいわゆる「IoT機器」などを、ごく自然に、ぼんやりと、見据えていた。
ただ、方向性をはっきりさせればさせるほど、教える授業になってしまうのではないかと、逆に不安が募ってくる。特に、それはASPのコンセプトと逆になってしまうのではないか。そもそも「プログラミング的思考」が腑に落ちないのに、さらにこの違和感と相まって、完全に消化不良のままとなってしまっていたのだ。
そのため、Scratchの先の方向性、例えば、夏休みの自由研究で大いに活用できそうな「データ分析」、たくさんの子どもたちが夢中になっている「ゲーム」、それからアクセサリーやおもちゃなどのいわゆる「IoT機器」などを、ごく自然に、ぼんやりと、見据えていた。
ただ、方向性をはっきりさせればさせるほど、教える授業になってしまうのではないかと、逆に不安が募ってくる。特に、それはASPのコンセプトと逆になってしまうのではないか。そもそも「プログラミング的思考」が腑に落ちないのに、さらにこの違和感と相まって、完全に消化不良のままとなってしまっていたのだ。
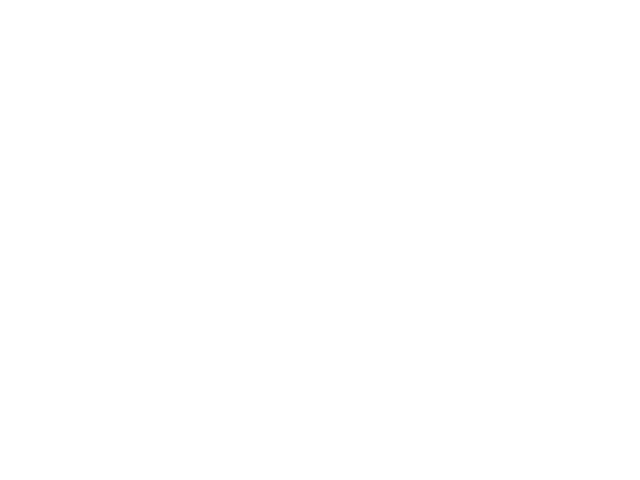
図2 Microsoft MakeCode Arcadeでゲームを動かす
3
そこで、改めてScratchの設計思想について調べてみた。Mediumというメディアがあるのだが、人間が書いた「いい記事」を読みたい人、人間味のある「いい記事」を書きたい人のメディアで、いわゆるLong Readsをじっくり読める場所だ。そこで探したところ、Scratchのチームがまとめて記事を書いている場所があり、そこで「A Parents’ and Guardians’ Guide to Scratch」という記事を見つけた。そして、そこに出てきたのが、設計思想の根底にある4つのPだった。下記で参照されている「GIVE P’S A CHANCE: PROJECTS, PEERS, PASSION, PLAY」に詳しく説明されているので、まずはこれから紹介したい。
Scratch is based on a philosophy called the 4 P’s of Creative Learning
4つのPとは、Projects、Peers、Passion、Playのことで、図3に示すcreative learning spiralの重要な構成要素だという。それは、まず、作りたいものを思い浮かべ(imagine)、それに基づいてProjectを作成する(create)、作ったもので遊び(play)、他の人に見せる(share)、そして総合的に振り返って(reflect)、また次に作りたいものを思い浮かべる(imagine)というスパイラルのことだそうだ。このスパイラルに、自分がcreateした場合だけではなく、他の人のProjectをshareされた場合も含め、繰り返し繰り返し関わってさまざまな経験を積むことで、次第にユニークな考え方ができるようになり、creative thinkerになっていく、と考えられている。
Projectsは、プログラミングを学ぶ時の一般的なやり方ではないというが、Scratchでも、学びながら作ることに変わりはないものの、最初からProjectを作る、つまり、creative learning spiralを回す、ということが、しっかり意識されているのだ。
Peersは、この一連の学習プロセスの中で中心的な役割を果たすものと最初から考えられている。creative learning spiralが、一人で学習するものではなく、一緒に学ぶコミュニティの存在を大前提にしているのだが、このコミュニティメンバーがPeersである。Peersは、audienceとinspirationの2つの役割を持っており、audienceとはProjectをshareしたときにフィードバックを返してくれる存在、inspirationは他の人がshareした作品を見て新たなアイデアを思いつかせてくれる存在だ。これを容易にする仕掛けが、ソフトウェアのライセンスで、Scratchで作成したProjectは、全てCreative Commons licenseになる。そのため、元の作者を明記すれば、自由にPeersのProjectに付け足しをしたProjectを公開できるのだ。これはremixと呼ばれ、creative learning spiralを機能させるのに大きな役割を果たしている。
Passionは、Scratchのコミュニティで共有されるProjectが多様性を見せるために重要な要素となる。例えば、写真や映像などのメディアは、プログラミングの学習の妨げになるのではないか、という声が多く上がったそうだが、子どもたちは写真や映像を使うのが大好きだ(Passion)。それならば、それをもっと使えるようにしてあげよう、そういう考え方が、Passionを支えている。
Playは、その単語から一般的に考える「楽しいこと」を意味しているのはなく、取り組む姿勢を意味している。新しいこと(つまりできないかもしれないこと)にチャレンジする姿勢や、限界を試してみることだ。これは、creativeなプロセスで中心的な役割を果たすので、積極的に取り組めるよう、backpackやdraftの機能が用意されている。backpackは、Projectで使用した画像や映像を、別のProjectで使えるようにするもので、draftは、やり方が分からない未完成のProjectを公開して、Peersからアドバイスをもらえるようにするものだ。
元の記事に戻ると、代表的なProjectの事例として、「Dance, Fleischer Cat, Dance!」が紹介されているので、動かしてremixしてみることをおすすめする。
また、保護者がどのようにScratchで学習する子どもをサポートしたら良いかについては、「家族が一緒にScratchをやる一番いい方法は、一緒に座って、いろいろやってみることです」とある。4Pを念頭に、creative learning spiralを回せるように、サポートしてあげること。これってつまり、家族もPeersとして参加する、応援するってことなので、ここまできて、ようやくASPへの関わり合い方が見えてきた。
Scratch is based on a philosophy called the 4 P’s of Creative Learning
4つのPとは、Projects、Peers、Passion、Playのことで、図3に示すcreative learning spiralの重要な構成要素だという。それは、まず、作りたいものを思い浮かべ(imagine)、それに基づいてProjectを作成する(create)、作ったもので遊び(play)、他の人に見せる(share)、そして総合的に振り返って(reflect)、また次に作りたいものを思い浮かべる(imagine)というスパイラルのことだそうだ。このスパイラルに、自分がcreateした場合だけではなく、他の人のProjectをshareされた場合も含め、繰り返し繰り返し関わってさまざまな経験を積むことで、次第にユニークな考え方ができるようになり、creative thinkerになっていく、と考えられている。
Projectsは、プログラミングを学ぶ時の一般的なやり方ではないというが、Scratchでも、学びながら作ることに変わりはないものの、最初からProjectを作る、つまり、creative learning spiralを回す、ということが、しっかり意識されているのだ。
Peersは、この一連の学習プロセスの中で中心的な役割を果たすものと最初から考えられている。creative learning spiralが、一人で学習するものではなく、一緒に学ぶコミュニティの存在を大前提にしているのだが、このコミュニティメンバーがPeersである。Peersは、audienceとinspirationの2つの役割を持っており、audienceとはProjectをshareしたときにフィードバックを返してくれる存在、inspirationは他の人がshareした作品を見て新たなアイデアを思いつかせてくれる存在だ。これを容易にする仕掛けが、ソフトウェアのライセンスで、Scratchで作成したProjectは、全てCreative Commons licenseになる。そのため、元の作者を明記すれば、自由にPeersのProjectに付け足しをしたProjectを公開できるのだ。これはremixと呼ばれ、creative learning spiralを機能させるのに大きな役割を果たしている。
Passionは、Scratchのコミュニティで共有されるProjectが多様性を見せるために重要な要素となる。例えば、写真や映像などのメディアは、プログラミングの学習の妨げになるのではないか、という声が多く上がったそうだが、子どもたちは写真や映像を使うのが大好きだ(Passion)。それならば、それをもっと使えるようにしてあげよう、そういう考え方が、Passionを支えている。
Playは、その単語から一般的に考える「楽しいこと」を意味しているのはなく、取り組む姿勢を意味している。新しいこと(つまりできないかもしれないこと)にチャレンジする姿勢や、限界を試してみることだ。これは、creativeなプロセスで中心的な役割を果たすので、積極的に取り組めるよう、backpackやdraftの機能が用意されている。backpackは、Projectで使用した画像や映像を、別のProjectで使えるようにするもので、draftは、やり方が分からない未完成のProjectを公開して、Peersからアドバイスをもらえるようにするものだ。
元の記事に戻ると、代表的なProjectの事例として、「Dance, Fleischer Cat, Dance!」が紹介されているので、動かしてremixしてみることをおすすめする。
また、保護者がどのようにScratchで学習する子どもをサポートしたら良いかについては、「家族が一緒にScratchをやる一番いい方法は、一緒に座って、いろいろやってみることです」とある。4Pを念頭に、creative learning spiralを回せるように、サポートしてあげること。これってつまり、家族もPeersとして参加する、応援するってことなので、ここまできて、ようやくASPへの関わり合い方が見えてきた。
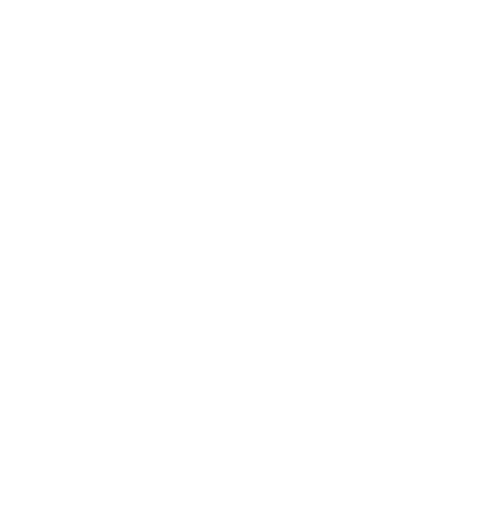
図3 creative learning spiral
4
小学校のプログラミング教育のねらいである「プログラミング的思考」がどうも腑に落ちなかったのは、教えることに重きを置いているため、問題解決能力が向上すると思えなかったためだ。一方、Scratchの設計思想には、creative learning spiralという考え方があり、実現したいことを思い描き、形にして、フィードバックやインスピレーションをもらって改良して突き進む、新しい問題に挑戦する姿勢や考え方、特に完璧主義に陥らずに突き進むエネルギーの出し方について、実践的に学べることがよくわかった。つまり、ねらいが、学ぶ内容(プログラミング的思考)にあるのか、学び方(creative learning spiral)にあるのか、そこに根本的な違いがあったのだ。
Microsoft MakeCodeから見据えた3つの方向性については、creative learning spiralを回しながら必要に応じて見せてあげるものであり、それ自体が間違っているとか合っているということではなく、「あくまでも子どもたちがcreative learning spiralを回せるようにサポートしてあげること」、それがScratch活用の鍵なのですね。
「何やっているんだい、すごいね」と隣に座って応援してあげるだけでも大丈夫。Scratchには、子どもたちがcreative learning spiralを回せる仕掛けが、こんなにも用意されているのですから。
Microsoft MakeCodeから見据えた3つの方向性については、creative learning spiralを回しながら必要に応じて見せてあげるものであり、それ自体が間違っているとか合っているということではなく、「あくまでも子どもたちがcreative learning spiralを回せるようにサポートしてあげること」、それがScratch活用の鍵なのですね。
「何やっているんだい、すごいね」と隣に座って応援してあげるだけでも大丈夫。Scratchには、子どもたちがcreative learning spiralを回せる仕掛けが、こんなにも用意されているのですから。
最後に
Scratchは、設計思想を改めて確認すると本当に素晴らしいツール、コミュニティですが、一方で、なんでもできるわけではありません。子どもたちがcreative learning spiralを回せるようになったら、いつか、もっと大きなspiralを回したいけど回せない、という時がやってきます。まずは、大きな方向性を念頭に、一緒にとことんやってみる。そしてその先にあるものを見せていく。Peersの一人としてコミュニティに参加し、みんなを応援しながら、活用方法を紹介していきたいと思います。
佐藤 剛宣
Takenori Sato
Takenori Sato
株式会社TMT代表取締役、健康エンジニア
山梨県北杜市明野町在住、妻と4人の子供の6人暮らし。趣味は自転車。これまでの経験を生かして、2024年からは、運動と遊びに取り組んでいる。Computer ScienceのInformation Retrieval(データを保存し、情報として取得する技術の総称で、データベース、検索エンジン、ビッグデータ基盤と分析からAIまで)関連スタートアップで20年の経験を持つ。
1998年(当時)運輸省航空大学校飛行機操縦課卒業
2005年 db4objects(シリコンバレーの組み込みオブジェクトデータベース開発スタートアップ)日本代表
2018年 EDGEMATRIX株式会社 常務執行役員
2024年 現職
1998年(当時)運輸省航空大学校飛行機操縦課卒業
2005年 db4objects(シリコンバレーの組み込みオブジェクトデータベース開発スタートアップ)日本代表
2018年 EDGEMATRIX株式会社 常務執行役員
2024年 現職
© 2024 All Rights Reserved
takenori.sato@gmail.com
takenori.sato@gmail.com

